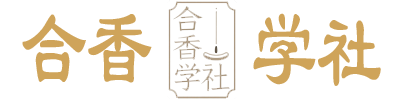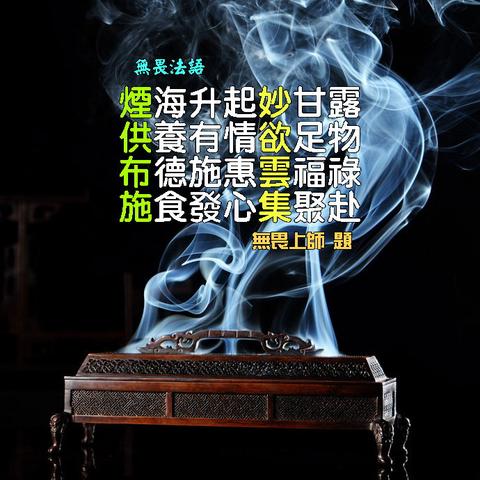2024年3月、タイの「通話門」事件によって引き起こされた数千人のデモは、現代社会の集団的な不安を映し出す鏡のような存在でした。路上で標語を掲げる若者たち、見物する人々の緊張した表情、ソーシャルメディア上で絶え間ない非難……これらの画面の中には、事件自体よりも注目に値するシグナルが隠されています。社会矛盾が激化するとき、個人の情緒的なストレスが目に見えて蓄積しているのです。
このようなストレスはタイに限ったものではありません。世界保健機関(WHO)のデータによると、世界で約10億人が精神健康問題に悩まされており、不安障害やうつ病の発病率は過去10年間で27%増加しています(WHO, 2023)。私たちの携帯電話は24時間振動し、仕事のグループにはいつも未読のメッセージがあり、住宅ローンや車ローンが二つの山のように圧し寄せ、ビデオを見るときでさえ「同世代の人はすでに成功している」という不安に取り巻かれています。情緒の波が胸を越えるとき、私たちには「情緒の出口」が必要です。そしてタイ人が選んだのは、香りを心のアンカーにすることです。

バンコクの黎明寺前では、朝の第一線の太陽光が必ず線香の煙と出会います。線香やロウソクを売る老婆はモリヤングを花串に編み、白檀の煙が仏像の前でゆらゆらと上がります。チェンマイの夜市では、香包の店の前にはいつも香材を選ぶ観光客が集まっており、店主は真剣にあなたに教えてくれます。「これは頭痛を和らげるカンゾウ、あれは安心させるオポポナックスです」。タイの香文化の根は、仏教信仰と熱帯気候の二重の土壌に深く根付いています。
タイの人口の95%が仏教を信じており、『大般涅槃経』にある「香は仏の使い」という理念により、香りは凡人と仏界をつなぐ媒介となっています。寺院では毎日の早課で必ず三柱の線香を焚き、信者たちは香りを使って祈りを表現します。この儀式自体が心理的な癒しの機能を持っています。両手を合わせて線香を捧げるとき、注意力が煩わしい現実から引き離され、呼吸が香りの流れに従って長くなり、不安が儀式感の中で希釈されます。
タイは熱帯に位置しており、高温多湿の環境ではカビが繁殖しやすく、人もイライラしやすくなります。地元の伝統医学である「タイ医学」では、「湿気が体に入ると気が鬱滞する」とされており、香りは辛くて温かく、「鬱滞を解き、精神を覚ます」効果があります。『タイ医学経典・薬香巻』には、「沉香、白豆蔻、香茅をそれぞれ等量取り、粉末にして焚くと、室内の汚れた空気を取り除き、心を安らげる」と記載されています。このような香りに対する実用的なニーズが、徐々に日常の癒しの習慣に変わっていきました。
タイの田舎では、主婦たちは台所にモリヤングの葉で編んだ香包を吊るし、「モリヤングの香りを嗅ぐと、野菜を切るときでもイライラしない」と言います。学生たちが試験前には、母親がボルネオコハクの香を焚き、「ボルネオコハクは冷たくて、頭がすっきりする」と言います。たとえ夫婦が口論した後でも、黙って安息香を焚きます。このベトナム産の樹脂の香りは、タイ語で「和解の香り」と呼ばれています。
私たちが「香りを嗅ぐと安心する」と言うとき、それは単なる心理的な暗示ではありません。現代の神経科学の研究によると、嗅覚は視床を経由せずに直接大脳辺縁系に入る唯一の感覚です(Shepherd, 2004)。この領域は情緒、記憶、自律神経機能を司っており、香りの分子は鍵のように情緒の「調節スイッチ」を直接開くことができます。
日本の香道研究所の実験によると、沉香の揮発油に含まれるセスキテルペン類成分は、血液中のコルチゾール(ストレスホルモン)のレベルを著しく低下させることができます(小林真一, 2018)。タイのチェンマイ大学で行われた比較実験では、30人の長期的な不安に悩む被験者が沉香の香りを15分間嗅いだ後、心拍変動性(HRV、ストレス状態を反映する指標)が平均23%向上しましたが、対照群ではわずか5%しか向上しませんでした。
タイはモクレンの原産地の一つであり、地元の伝統ではモクレン茶でうつ病を和らげるのは偶然ではありません。フランスの神経科学研究所の研究によると、モクレンの香りに含まれるベンジルアルコールは、脳内でセロトニン(「幸せホルモン」)の分泌を促進し、その効果は低用量のSSRI系抗うつ薬と同等です(Lecrubier, 2015)。これが、タイの女性が生理中や出産後に、必ず枕元に新鮮なモクレンを置く理由を説明しています。
インドのアーユルヴェーダ医学とタイの伝統医学では、白檀を「心の薬」と見なしています。アメリカのジョンズホプキンス大学のfMRI(機能的磁気共鳴画像法)研究によると、白檀醇は大脳前頭前野皮質を活性化させることができ、この領域は情緒調節と合理的な意思決定を担当しています(Bush, 2020)。私たちが白檀の香りを嗅ぐと、脳は「戦うか逃げるか」のストレスモードから「リラックスと回復」の平静なモードに切り替わります。

タイのデモ事件の参加者たちは、香りの背後にある科学的な原理を知らなかったかもしれませんが、混乱の中で線香を焚く本能は、人類最古の癒しの知恵に呼応しています。私たちこれらのストレスに取り巻かれた都市人にとって、香文化は遠い儀式ではなく、日常に溶け込むことができる「情緒管理ツール」なのです。
コンピュータの横に香立てを置き、柑橘系の香りの線香(レモングラス+スイートオレンジなど)を選びましょう。研究によると、柑橘系の香りは仕事の効率を20%向上させると同時に、落胆感を30%軽減することができます(Morimoto, 2019)。仕事の案が何度も却下されたとき、それを焚き、目を閉じて深呼吸を三回し、香りが「私にはできない」という考えを「もう一度試してみることができる」という考えに置き換えましょう。
タイの主婦たちの知恵を借りることができます。台所で料理をするとき、鍋にモリヤングの葉を数枚入れるか、レンジフードの横に香包を置きましょう(レシピ:バラ3g+カンゾウ2g+陳皮1g)。香りは目に見えない仲介者のように、非難の言葉を口元で柔らかくします。心理学の研究によると、快適な香りの中にいる夫婦は、口論後の和解速度が40%速くなります(Haviland – Jones, 2005)。
多くの人が寝る前にスマートフォンを見ると、ますます目が覚めてしまいます。そんなときは「香り療法代替法」を試してみましょう。寝る1時間前に電子機器を切り、ラベンダー+オポポナックスの合香(比率2:1)を焚きます。ラベンダーに含まれるリナロールは深い睡眠の時間を延ばし、オポポナックスの酢酸オクチルは不安を和らげる作用があります(Lis – Balchin, 1999)。香りが部屋に広がると、100本目のビデオを見るよりも眠気が早く訪れることがわかります。
タイのデモ事件はやがて収まるでしょうが、現代社会のストレスは消えることはありません。私たちが必要なのは「瞬間的な癒し」の魔法ではなく、タイの香文化のように——癒しを日常に溶け込ませ、香りを生活の一部にすることです。
私たちがオフィスで線香を焚くとき、それは粋を装うためではなく、緊張した神経にやさしい緩衝を与えるためです。私たちが台所でモリヤングの葉を煮るとき、それは故意に懐古するためではなく、生活の香りに癒しの温度を少し加えるためです。私たちが寝る前にオポポナックスの香りを嗅ぐとき、それは儀式を追求するためではなく、一日中忙しかった自分自身に、「お疲れ様でした」と言うやさしい方法を与えるためです。
香文化の最も魅力的なところは、おそらくその「無意識さ」にあるのでしょう。複雑な香道の儀式を特別に学んだり、高価な希少な香材を買ったりする必要はありません。一本の線香、一束の花、さらには乾燥したモリヤングの葉でさえ、あなたが不安と戦う武器になることができます。
この息を切らして争う時代で、香りが私たちにゆっくりすることを教えてくれましょう。ストレスを避けるのではなく、ストレスの中で自分自身に心の浄土を残す方法を学ぶのです。畢竟、本当の強さは、ストレスに倒されないことではなく、倒された後にも、なじみのある香りを嗅ぎながら、ゆっくりと立ち上がることなのです。
【創作は容易ではない】転載や交流については、合香学社までご連絡ください
参考資料
1. World Health Organization. (2023). Mental Health Atlas 2023.
2. Shepherd, G. M. (2004). The Synaptic Organization of the Brain. Oxford University Press.
3. 小林真一. (2018). 沉香揮発油對壓力相關激素的影響研究[J]. 日本香道學會會報, (32), 45 – 52.
4. Lecrubier, Y. (2015). Jasmine scent and serotonin levels: A pilot study[J]. Journal of Psychopharmacology, 29(3), 289 – 294.
5. Bush, G. (2020). fMRI study of sandalwood odor effects on prefrontal cortex[J]. NeuroImage, 210, 116532.
6. Morimoto, K. (2019). Citrus aroma and work efficiency: An experimental study[J]. Journal of Environmental Psychology, 65, 101382.
7. Haviland – Jones, J. M. (2005). An environmental approach to positive emotions: Odors and facial muscle responses[J]. International Journal of Psychology, 40(3), 118 – 126.
8. Lis – Balchin, M. (1999). Aromatherapy: A Systematic Review of Randomized Clinical Trials[J]. Phytotherapy Research, 13(5), 395 – 401.